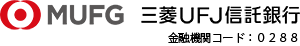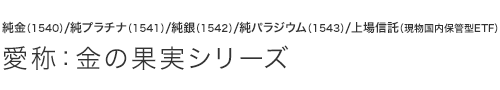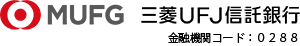山高ければ、谷深し。
3,000ドルまで本格調整局面もなく、一気に突っ走り、前代未聞の大台を突破して、なおモメンタムによる新規買いが上昇圧力として期待されている。NY金市場の最前線では、AIを駆使したプログラム売買が多用され、買いが買いを呼ぶ展開になりやすい市場環境が形成されている。
そこで働くゴールド・トレーダーたちも、金専門家ではなく、行内人事異動で、株式・債券・外為部門から転任してきた人たちが目立つ。それでも一人前としてやってゆけるのは、金ETFの普及により、金の金融商品としての面が強くなり、コモディティーとしての面と同様、或いは、時として、それを凌ぐインパクトを特に短期的価格形成に与えているからだ。
金市場が長期的需給均衡点を探る過程で、短期的乱高下のレンジが急激に拡大しつつある。金ETFが、本来、年金基金の長期的金保有のために商品開発されたが、実際には手数料引き下げ競争の中で投資家の短期売買ツールとして人気化したからだ。金ETFのNY市場と東京市場の上場に直接関与した者としては、意外な展開になった。
このような市場環境の中では、金の長期保有が見込めるのは、公的部門の中央銀行と、インド中国など文化的金選好度が高い新興国の現物購入だ。この二部門が、金価格の底値を切り上げてきた。
その上に、新雪ドカ雪の如く積もったのが、ヘッジファンドなどの投機的購入だ。グローバル・マクロ系でも、金保有は長くて2-3年が目途というところか。CTA(コモディティー・トレーディング・アドバイザー)などの超短期系ともなれば、1週間程度で売買を繰り返すことが珍しくない。このような参加者抜きでは、短期間で3,000ドル突破など、いくらトランプリスクヘッジという「錦の御旗」を掲げても、あり得なかったであろう。特に、地政学的リスクを囃す金買いには要注意だ。陳腐化しやすい材料ゆえ、「噂で買ってニュースで売る」というような手口に利用されがちだ。
結局、煽られた個人投資家(投機家?)が、梯子を外され、高値掴みに泣く事例を、どれだけ見せつけられてきたことか。NISA世代の諸君に、筆者は、「有事の金のドカ買いは、悪魔の選択」と語り、戒めている。
なお、ニュースにはならないが、潜在的に巨大な売り要因が、歴史的高値圏では控えている。それがリサイクルだ。金は腐食しないので、有史以来採掘された金のストックが、「地上在庫」として、推定216,000トンほど地球上に存在する。年間金生産量は3,600トンほどゆえ、地上在庫のほんの一部が、高値につられて金市場に還流してくるだけで、金価格には強い下げ圧力がかかる。既に、世界的に、金買い取りインフラが整備されてきた。この「金売り戻し現象」には特徴がある。人間の欲として、出来るだけ高く売りたいから、市場が強気予想に満ちているときは、お宝を手放さない。しかし、なんらかの理由で、相場が下げに転じると、我先に、換金売りに走る。一人の売る量は少ないが、世界的に数百万人が一斉にリサイクル店に押しかければ、国際相場を動かす力を持つ。ボディーブローのごとく、じわり、マーケットに効くのだ。
以上の状況を考慮すれば、今年前半は、株式・債券・外為市場を覆う不確実性が晴れず、金価格が3,300ドルをつけることもあり得る。しかし、その持続性はかなり危うい。ひとたび、金市場を囲む環境が変化すれば、2,500ドルまで急落しても全く不思議ではない。
それでも、歴史的には、超高値圏なのだ。
【添付写真】 アテネの金買い取り店(筆者撮影)