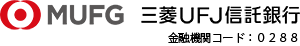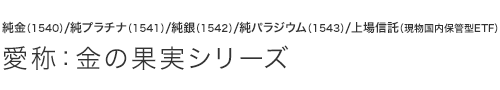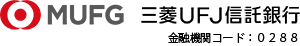金の世界で、ロンドンといえば、ロスチャイルドの「黄金の間」で毎日2回行われる「gold fixing 金建値決め」が有名であった。世界中から金現物の売買注文が、ロンドン市場の5社に集まり、売り・買いの注文が飛び交い、当日の建値(午前1回、午後1回)が決まった古き良き時代であった。
しかし、このロンドン金市場のギルド的側面が問題視され、インター・バンクの金売買に変質していった。金国際価格決定の主導権は、NY市場に握られた。ロンドン側も、LBMA(London Bullion Market Association)を強化して対抗したが、もはや、価格形成力をNY市場が握る状況は変えられなかった。
LBMAもWGCもプラチナ・カウンシルも、所詮、業界団体で、販売促進機関だ。金・プラチナの国際調査機関と説明されるのは日本だけ。フィナンシャルタイムズは、WGCを「a trade body業界団体」と表記している。
いっぽう、NY金市場は、売り手と買い手がぶつかりあう場を提供する。勝てば官軍の世界。ゴールド・トレーダーたちも、人事異動で、株・外為・債券担当から金担当になった連中が多い。ゆえに、金の知見は薄い。それでも金を金融商品として売買することは、株や外為市場と同じ仕組みゆえ、抵抗感は薄い。しかも、大きな取引に慣れている。
金3,000ドル台の背景には、市場の変質が起こっているのだ。