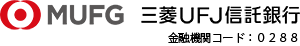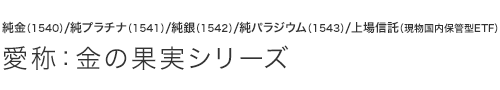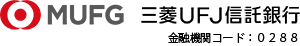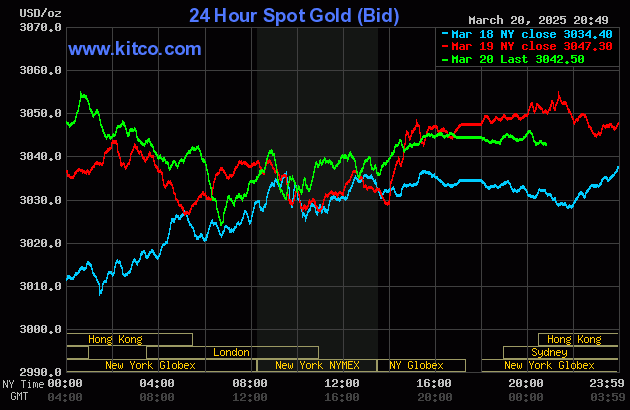
24年は、FRBが適度な物価上昇と雇用を実現させる「ソフトランディング」(経済軟着陸)がNY株式市場で囃され、ウオール街に年間流行語大賞でもあれば、おそらくトップになるほどであった。それが、25年、トランプ政権の時代となるや、市場の景色が激変。ソフトランディングなど「懐かしい昔話」と化し、経済の軟化を意味するソフトエコノミーが、今年のマーケット・リスクとして急速に浮上中だ。
ソフトといえば、米国経済指標も、GDPや雇用者数などの「ハード・データ」より、ミシガン大学消費者信頼感指数などの「ソフト・データ」の悪化が懸念されている。
3月FOMC後のパウエル議長記者会見でも、ソフトエコノミーの実現性についての質問に、「基本シナリオは、外的要因による一過性(transitory)の物価上昇を排除せず」と答えた。その瞬間にマーケット関係者の頭をよぎったのは、コロナ後のインフレをパウエル氏が頑固に「一過性」と論じ、痛恨の判断ミスを犯したことだ。FRB経済見通しについても「現在のように極めて不確実性の高い経済環境で、予測を変えるということは、率直に言って、無力感もある。長期的な見通しは変わらず、という程度にしておけば無難だ」と本音をちらつかせた。公の席で無力感(inertia)と言う単語を使うことは異例だ。そうあっさりと言われてしまうと、市場の合言葉も「FRBには逆らうな」から「FRBを疑え」に急変してしまう。
今回は、3か月ごとに発表されるFRB経済レポートも発表され、特にFOMC参加者の金利見通し分布を示す「ドット・チャート」が特に注目された。中心値が、年内利下げ2回ということが特に報道されたが、「関税インフレ」の影響を誰も予測できない時点での金利見通しなど、それこそ「無力感」に満ちた数字と受け止められてしまう。
結局、いつものように「データ次第」、特に「トランプ経済政策次第」ということになろう。
そのトランプ氏は「FRBは金利を下げたほうが遥かに良い」とSNSを通じて吠えた。
ご心配なく。あなたの関税政策などで、景気後退は不可避の情勢ゆえ、少なくとも、あなたも認めたとおり「移行期間中」は金利が下がり、お望みどおり「ドル安」圧力も強まりますよ。
但し、インフレと景気後退が同時に進行する「スタグフレーション」の可能性が強まる場合に、誰に責任転嫁するか、今のうちから考えておいたほうが良いですよ。
そして、あなた個人のポートフォリオに、自分が引き起こすリスクのヘッジのために、金を、しっかり持っていますか?(笑)