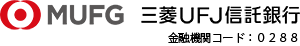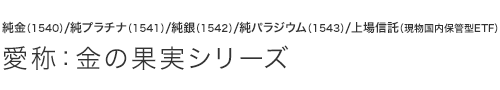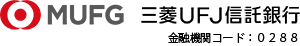首題の記事が昨日26日日経朝刊一面トップに載った。
2021年も、タイが90トン、インドが70トン、ブラジルが60トン。昨年はポーランドが100トン。
かなりまとまった量の金が公的セクターで外貨準備として購入されている。
対して、外貨準備の核となる米ドルは減少傾向だ。
その背景には、未曽有の規模のFRB量的緩和により、米ドルの価値が希薄化したことが挙げられる。
筆者流にいえば、金を購入するという行動はドルへの不信任票。
量的緩和により、いくらでも「刷れる」ドルから、絶対に「刷れない」現物の金にシフトしている。
特に最近目立つのは新興国中銀による公的金購入だ。
アジア経済危機などで自国通貨が売り込まれ、大量のマネーが流出した苦い記憶が残るので、危機への備えとして無国籍通貨(発行主体がなく、即ちソブリンリスクがなく、且つ、ナショナリズムの匂いがしない)=金を購入しているのだ。
米国の量的緩和縮小、ゼロ金利解除、そしてFRB資産圧縮と、FRB金融政策が引き締めに向かえば、新興国からのマネー流出は加速化して、危機的状況に陥るケースも想定される。
そのような事態に備え、金準備を防波堤に見立て、経済ショックを吸収するための公的金購入が増えそうだ。
但し、経済危機という有事が実際に起これば、金準備の一部を売却して有事を凌ぐというケースも生じるであろう。
「有事の金」の本当の意味は売って凌ぐことにあるのだ。
金価格予測に於いても、公的金購入は長期保有なので重要だ。
ジワリ金価格の下支えとして、下値を切り上げる効果がある。
歴史的視点では、1990年代から2000年代初頭にかけて、欧州の中央銀行が相次いで数百トン規模の金売却を行った。
当時は、「これからは有事のドルの時代」と言われ、金利もつかない金は用無しと見做された。
その結果、金価格は250ドル、円建てで1,000円割れという、今では信じられない底値をつけた。
その後、中銀セクターで公的金売却を自主的に控えるための協定が締結され、金の下げは止まった。
そして、リーマンショックを契機に、米国経済の脆弱性が露わになるや、国際基軸通貨としての米ドルの信認は低下して、ドルの代替通貨として金が買われるようになったのだ。
金の年間需給データでは、公的分野が年間500トン程度の「供給項目」から年間数百トンの「需要項目」に移った。
その供給量から需要量への絶対差は年間ベースで500~1,000トンに及ぶ。
年間生産量が3,000トン台規模の金市場には大きな需給要因だ。
大量に公的金売却した欧州主要国中銀は、結果的に、とんでもない安値で金を売り払ったことになり、トラウマになっている。
例えば英国は400トン以上の金を平均価格275ドル!で売り払い、後日、議会で野党の追及材料になった。
なお、外貨準備として、プラチナや原油を保有する国はない。
金は通貨とコモディティの二面性を持つ貴金属なのだ。
それから、ドルに対する信認が低下しているというが、外為市場はドル高ではないか、という反論もある。
これに対する答えとしては、ドル信認低下は長期的現象で、日々の外為市場でのドル高・ドル安とは異次元の話ということだ。
相場を見るには現場を見る「虫の目」と、潮流を見る「魚の目」と、歴史的に俯瞰する「鳥の目」が必要である。
更に、そうはいっても、ドル決済システムなしで世界経済は回ってゆかない、との議論もある。
これは事実だ。
そこで、世界的通貨覇権への対抗措置として「最適通貨圏構想」を米マンデル教授が唱え、ユーロが創設された。世界共通通貨は政治的に無理筋なので、地域の基軸通貨を考えよ、との構想だ。
米大陸はドル、欧州はユーロ、アジアは人民元か円か、そして中東は金。
金本位制に回帰することはあり得ないが、金の裏付けのない信用通貨制度も限界がある。
振り子が金本位制から信用通貨制度に振り切ったところで、元の方向に戻り始めたものの、金本位制まで振り戻すことはなく、その中間で、外貨準備として金を組み入れる動きが顕在化している、ともいえる。
そもそも金本位制は性悪説、信用通貨制度は性善説に基づく。
中央銀行総裁も人間ゆえ間違えることもある。
そこで、人間の力が及ばぬ独自の希少価値を持つ金を組み入れることも必要なのだ。
更に、我が日本国の公的金準備は846トン。
世界第二位の外貨準備を持つのに、これは少なすぎる、との素朴な疑問もある。
基本的に日銀が金を買う行為は、ドル不信任票と見做されかねないので、外交配慮上、公的金購入を控えているのだ。
その代わり、米国の借金証文である米国債をしこたま保有している。
その米国は、「金廃貨」の方針を明示しているのに、公的金保有量は断トツの8,133トン。
日本の約10倍。
日本国民感情としてはモヤモヤ感が残るところだ。
そこで、日本人は個人的に金を保有して経済有事に備えよ、というのが筆者の持論だ。